_____熱海土石流原因究明プロジェクトチーム : 令和3年7月3日静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害の原因究明・行政対応検証を行っています
松山市主催 住民説明会明Resident briefing hosted by Matsuyama City
松山市主催 住民説明会 2025/02/25 動画+発言録
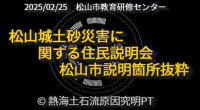 ~松山市主催住民説明会 松山市・市長の説明部分抜粋~
~松山市主催住民説明会 松山市・市長の説明部分抜粋~
2025/02/25 松山市主催住民説明会
~ 松山市・市長の説明部分抜粋 ~
定刻となりましたので,ただいまから
緑町土砂災害に関する住民説明会を開催いたします。
本日はお忙しい中、説明会にご出席いただきありがとうございます
私は本日の進行役と努めます〇〇でございます。お願いたします。
本日説明会は1月30日に開催された
松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会での結果を受け
緑町で発生した土砂災害について
お手元の次第に従ってご説明させていただきます
説明は15分程度の予定です
皆様からのご質問は説明をえ全て終了した後
一括してお受けしたいと思っております
円滑な進行にご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。
それでは、これより説明に入ります
始めに市長からご説明いたします
能世市長
本日はお忙しい中この住民説明会に
お忙しい中、また寒い中
ご参加をいただきまし誠にありがとうございます。
初めに昨年の7月12日に城山で発生を致しました
土砂災害で亡くなられた方々に心から哀悼の意を示しますとともに
またご遺族の方々に心からえお悔みを申し上げます
また被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。
松山市といたしましては被害に遭われた方々が
元の生活に戻れる環境を整えることを
最優先に取り組み
これまで二次災害の防止対策を出来るだけ早く完了させ
生活再建金の給付や、再発防止に向けた取り組みを進めてまいりました
その中、愛媛県が設置した
松山市緑町土砂災害対策技術検討委員会の検討結果が
1月30日に取りまとめられ、
皆様に説明させていただく準備が整いましたので
・・・・・・・・・・①
本日住民説明会を開催させて頂くことになりました。
本日の説明会ではその結果を元に
専門家の意見を踏まえて確認した
緊急車両用道路の、設計・施工の妥当性や
本件、災害発生所の管理の瑕疵の有無について
また再発防止に向けた本市の取り組みについても
説明をさせて頂きます。
まず、詳細について担当から説明をさせて頂きます。
担当
それでは詳細説明をさせていただきます。
以下着座にて失礼致します。
ますお手元にある資料か、前方のスクリーン、
又はお近くのモニタ―、など見やすい方で資料の
ご確認をよろしく願いいたします。
まず、1ページ目
災害の発生メカニズム、
緑町で発生した土砂災害はどのようにしを起ったのか
技術検討委員会報告書などを元に説明させて頂きます
2ページお願いします
被災の概要は昨年7月12日で早朝
松山城北側斜面で土砂流出が発生、松山市緑町1丁目において
住宅等が被災しました。
被災状況は3名の方がお亡くなりになり
住宅被害は全壊3棟、一部損壊12棟、
非住宅被害は全壊1棟、半壊1棟です
3ページをお願いします
委員会の報告書には発生メカニズムの取りまとめでは
1.斜面変形
2.土砂流出
3.土砂流下
の、3つの段階を経て災害が発生したと推定されています
また、緊急車両用道路については
災害が発生した土砂流出時までには道路擁壁を撤去しており
2.土砂流出の危険となるような
直接の影響を与えた可能性は低いが
安定計算などから、1.斜面変形には、道路の擁壁、
盛土加重が影響を与えた可能性があるとされました
専門的な表現が多い為もう少し詳しく説明させて頂きます
4ページにお願いします
土砂災害の状況ですが、緊急車両用道路付近の
谷最上部から緑町がある谷末端部までの
約250mの区間で、土砂災害が発生しました
斜面変形と斜面崩壊は異なるものであり
先ほどの報告書にある、
①斜面変形は古くは松山城築城時から
今回の災害発生までの期間の中で
色々な原因で斜面が変形したと推定されています
斜面崩壊である、
②土砂流出と、③土砂流下は昨年7月12日に発生した
土砂災害そのもので、報告書では
緊急車両用道路が直接影響した可能性は低いとされています
5ページをお願いします
斜面変形は軟質な捨て土、
樹木の成長、道路過重つまり土や樹木また道路など
それぞれが影響した可能性や
警報クラスの大雨により変形が確認されることから
水の流入が影響した可能性など複数の原因が影響し
斜面変形が発生したと推定されました
6ページお願いします
斜面変形に影響を与えた可能性の捨土とは
松山城築城以降に
谷最上部の斜面に盛られていた土砂であり
瓦片を含んでいる場所があるなど
地層毎に異なった性質を持っていた他、
土は軟質だったと考えられます
7ページお願いします
次に斜面上にあった樹木ですが
被災前に飛行機から測量したデータからは
左下にカラーになっている地点がございます、
こちらの方で赤色で表示いる部分で
赤い枠で囲っている部分になります
こちらには30mを超える巨木だけではなく、
そこから更に松山城の斜面側登っていく方に向かって
黄色でありそして緑の方になってきます。
これらは15mから30mの樹木が多数あったことが確認されています
8ページをお願いします
緊急車両用道路は新たに整備したものではなく、
以前から使用していた管理道の改良を目的に
平成27年に建設しました
右上に断面図がございます
こちらからを見て頂きますと、擁壁の高さは最大で2mとなっています
技術検討委員会の検討結果では
試算で行った道路荷重を考慮した安定解析から
安全率の低下が確認され、この結果により
何らかの影響を与えた可能性があるのでは無いかとされています
9ページをお願いします
残された記録の中では大雨が降った際
斜面変形に関連すると思われる事象が発生しています
委員会の地下水解析の調査結果
こちらが左下の方のカラーの方の丸の部分になります
こちらの結果から、通常の道路施工や管理では把握が困難な
斜面内の地下水が
崩壊斜面下部、青色の丸で囲んた部分です
こちら側の方に集まるようになっていたことや
崩壊斜面下部から中腹は地下水が上昇しやすい
地形・地質だったことが確認されてい
10ページをお願いします
現地調査では、
雨が降った際に天守広場や道路付近の表面上の水の流れは
今回被災した道路があるAか所の斜面
今回被災した部分、色が強くなっている、
茶色く塗られている部分がA斜面になります
こちらの方に流れるのではなく
南側にある矢印が書いてる方になります
こちら側の方のB斜面の方に水が集中していることや
また11月2日の豪雨際には、青色の点線の枠で囲んてる部分に
この付近に湧水が確認されています
以上の結果から、緊急車両用道路付近は
降雨の影響を受けにくい地形だったことが確認されています
11ページをお願いします
昨年7月12日に発生した土砂災害に直接関連する
②土砂流出と、③土砂流下について説明させて頂きます
③土砂流下は②土砂流出後に斜面上に残された
一部の土砂が水を多く含み、泥のようになって流れたものです
②の土砂流出について説明させて頂きます
報告書には2つの可能性が示されました
まず、可能性1は地下水安定解析の結果より
斜面中腹から斜面下部で地下水位が上昇し
斜面の安全性が低くなり崩壊が発生したもので
緊急車両用道路が直接影響した可能性は低いとされています
青色の点線で囲っでいる部分というのが
大体、中腹から下部の方になりましてこちら
こちら側の方で斜面が崩壊する形になりました
それでですね、順次追いかけるように
いわゆるダルマ落としのように、
下が支えるところが無くなりましたので
地滑りのような現象が起きたのでは無いかと言うのが
可能性1です
12ページお願いします
可能性2は地水解析の結果より斜面下部では
下部周辺は水が流入集中しやすいとなる傾向があり
高さ30mを超える樹木の倒木が発生したことで
斜面崩壊は上部に向けて拡大したもので
緊急車用道路が直接影響した可能性は低いとされています
こちらもちょっと図面の方でですね
先ほどの解説させて頂いている部分で
まず水がですね、1番下の部分に多く溜まりやすい状況が
確認できております
そして、樹木の説明させて頂いたところもそうだったのですが
赤いのですね、多く30mを超える樹木というのがですね
この部分にありました。ここですね、
水の影響か、何らかの影響で倒れたということでですね
この部分が崩壊した形になり、そこを起点に上に順々に崩れて
いく事が起こったんではないかというのが可能性2となっております
つまり、可能性1及び、可能性2のどちらであっても
道路から離れた場所が災害発生の起点となったと推定されています
続いて緊急車両用道路の
設計・施工・管理の妥当性などについて説明させて頂きます
14ページを、お願いします
緊急車両用道路を整備する前に
現地では管理道路がすでに整備されていて
道幅は十分あったことや
工事で道幅が広がっていない様子少し分かりにくいですので
左側の方の写真になります。赤の点線部分については
以前の管理道の勾配は、急だった様子が確認できます
14ページを、お願いします
まず、緊急車両道路の整備目的を説明します
左側の図面は上から見た平面図と言われるもので
右側の図面は道路の勾配を表す図面です
右上の青色の線が、工事前で先ほどの写真で
見た付近は勾配が急になっています。そこで
緊急車などの通行に支障が無いように、緑色の線のように
勾配を緩やかにする事を目的とした工事でした
15ページを、お願いします
今回、緊急車両予道路の設計・施工に関する
妥当性の確認手段・手順として
まず、確認内容や手順などについて専門家に
意見を伺った結果
技術検討委員会が適切に調査を行っており
道路に関する追加の調査を実施しても
成果を得ることは難しいとの意見を伺いました
また道路の設計・施工に関する打当性の確認は
当時とは別の設計コンサルタント会社に一部の業務を委託し
市が確認を行う手順で実施することが望ましいとの
意見を伺いその意見を参考に市が確認を行うこととしました
その後、確認結果に関する専門家の意見を伺った後
最終的な市としての見解を決定しています
17ページを、お願いします
確認結果は道路構造令や道路土工指針などの
基準を参考に、設計内容を照査した結果
当時の現場状況を考慮した設計でも通常必要とされる
基準を満たしており問題がないことが確認されました
また施工の妥当性は、工事完成図書を確認した結果
本市の土木工事共通仕様書で定めている基準を
満たしていることを確認しました
こちらは、まず施工に関してはですね
いわゆる構造物の出来形、きちんとした寸法ができているかどうか
また今の埋め戻しの品質管理ということで
きちんとした埋め戻しがされていたか
また3番の方でですね
実際、擁壁を施工した際のコンクリート等がですね
きちんとした品質管理に基づいたものでしていたかという
ことに対しての確認を行っております
18ページを、お願いします
次に、緊急車両用道路の管理状況について説明させて頂きます
まず、左側の写真ですが平成30年7月豪雨時に発生した
ひび割れの補修跡が確認できます
この割れが発生した以降は市や指定管理者が
実施する日常点検の際に確認をしていましたが
さらにひび割れが広がるなどの変化は無かった為
令和6年6月30日までは緊急性はないと
判断していました
その後、右の写真こちらは7月1日の写真ですが
その後7月1日に道路に変状が発生した為、緊急性があると判断し
擁壁の撤去などの緊急対応を決定しました
19ページを、お願いします
昨年7月11日の写真ですが
緊急対応完了後、撤去部分に
降雨が影響しないようブルーシートを設置し
その後、災害が発生する12日まで毎日の点検を行っていました
その後6年7月で最大の雨量となった日もありましたが
災害前日の段階までは左側の写真の通り異常はありませんでした
また、右側の12日の写真ですが災害が発生した時点での
道路部分は大きな異常は見られませんでした
20ページを、お願いします
こちらは被災後の、道路付近の状況ですが、
技術検委員会で実施された調査からは
道路はブルーシートで保護されていた他、道路上に設置された
土のうやパイロン三角コーンのことですね、の、ずれがない事や
表流水の流下跡がないなど、道路付近は
災害による大きな変状は見られなかった事が確認されています
21ページを、お願いします
緊急車両用通路及び、斜面の管理の妥当性に関しては
次の(1)~(3)の事項について確認を行いました
まず災害が発生した区域はこれまでに
同様の災害が発生していないこと
土砂災害警戒区域から除外されていること
災害の誘引とされる、雨水は表流水だけではなく
把握することが困難なだったことを確認しました
地下水が斜面の不安定化に関連したとされること
道路から離れた場所が災害発生の起点となったこと、などが
推定されているなど
通常の道路施工や管理では今回の災害の予見は
難しい状況だったことを確認しました
また、令和6年7月1日に発生した道路の変状に対しては
対応を適に行っている事や
斜面を含む松山城跡は文化財保護法により国の史跡に
指定されているが
日常点検や倒木の恐れのある樹木の撤去土砂流出の確認などは
市や指定管理者により行われている事を確認しました。
これらの確認結果から緊急車両用道路の
設計・施工・管理は妥当であること
また技術討委員会の検証結果からも、明らかの通り
極めて複雑なメカニズムで発生したものであることなど
本市としては、今回の災害を予見したり
その結果を回避することは不可能であったと言わざるを得ませんので
問題があったとは言えないと考えております
最後に本復旧工事の進捗と
今後の安性向上への取り組みについて説明します
23ページを、お願いします
まず、今後復旧を予定している緊急車入道路を含む
管理道の必要性について説明させていただきます
今後も文化財としての城山を適正に管理していく為だけではなく
城山周辺の安全を確保する上でも重要視されている
樹木の管理を行う為に緊急車両用道路を含めた管理道は
必要不可欠なものとなっています
図面でも分かるように天守、石垣付近の管理道は
北西側には通行できないため
樹木管理などで平和通り側や
古町口登城道方面に向かうためには
今回、被災した緊急車両用道路を利用した管理道を
使う必要がありますのでご理解をよろしくお願いいたします。
24ページを、お願いします
これまでの説明会の中で城山の自然に調和しながら
地域の安全性を確保しほしいとの住民の皆様からのご意見などを
参考にした本復旧計画は先日の委員会で、了承されました
25ページを、お願いします
本復旧対策の詳細については
今年1月17日の説明会の内容と
重複する説明となるため
詳細な説明は割愛させていただきますが
誘引と考えられる公務への対策だけではなく
影響した可能性がある
素因・要因についても対策を実施していきます
26ページを、お願いいたします
本復旧工事の予定ですが工事業者が決定した際に
環境対策や安全対策などを含めて住民の皆様にお知せしながら
愛媛県が実施する工事と連携し
令和7年度中に完了することを目指しています
27ページを、お願いいたします
最後に今後の安全性向上への取り組みについて
説明いたします。城山周辺の安全性の取り組みについては
技術検討委員会から、現状を把握しなければならない課題として
Ⅰ.巨木の存在
Ⅱ.軟質な捨て土の分布
Ⅲ.降雨による水の流入
その他考慮すべき課題として城山周辺で
今後、施設を設置する際には対策を実施していく必要があるとの
提言がありました。これらの提言について市として速やかに対応して
いく必要があると考えております
以上で、担当課からの説明を終わります。
最後に、市長から説明させて頂きます。
先ほど担当からご説明をさせて頂きましたが
本市として緊急車両用道路の設計・施工の妥当性や
本件災害発生箇所の、管理の瑕疵の有無について
専門家の意見も踏まえて確認をした結果
緊急車両用道路の設計・施工に問題は無かったと判断しました
また本市として本件災害の発生を予見したり
その結果を回避することは不可能であったと
考えられますので、その管理に瑕疵があったとは言えず
従いまして公の営造物が通常有すべき
安全性を欠いていたとは言えませんので
国家賠償法につく賠償は難しいと判断しました
再発法施策については、技術検討委員会から指摘された
松山城の斜面が抱える課題に対する安全対策は
非常に重要であると認識しています委員会の提言を精査し
今後の安全対策と、本復旧工事について
迅速に対応してまいります
なお、本復旧工事は住民の皆様から頂いたご意見を踏まえ
技術検討委員会で承認をいただいた内容で
令和7年度の完成を目指して
皆様が安心して生活できるよう全力を尽してまいります
引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますよう
お願い申します
以上で本市からの説明を終了しました
熱海土石流原因究明プロジェクトチーム
連絡先:Mail:shimizu@cim-tech.jp